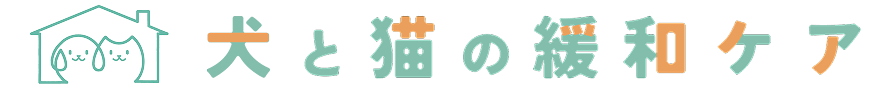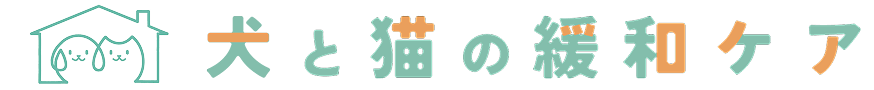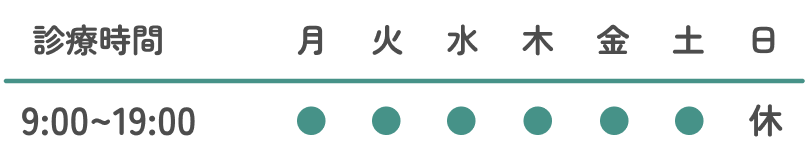犬の気管虚脱の末期症状|自宅でできる緩和ケアを獣医師が解説
気管虚脱とは、空気の通り道である気管が潰れてしまい、空気をうまく取り入れられなくなる病気です。
気管虚脱は進行性の病気で、最終的には呼吸困難により亡くなってしまうこともあります。
「愛犬が気管虚脱と診断された」
「今は元気だけどこの先どうなってしまうのかが不安」
「末期状態になったら何がしてあげられるか知りたい」
今回は、このような愛犬の気管虚脱に悩む飼い主様に向けて
- 気管虚脱の概要
- 生活するうえで気をつけていただきたいこと
- 末期状態の気管虚脱の犬に対する緩和ケア
を解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、愛犬の病気と向き合う参考にしていだければと思います。
気管虚脱とは
気管虚脱とは、気管が潰れて十分な空気を通せなくなる病気です。
鼻や口から吸い込んだ空気は気管を通って肺に入り、肺で空気中の酸素と血液中の二酸化炭素を交換して、気管を通って口や鼻から出ます。
通常であれば気管軟骨と気管の筋肉がしっかり筒状を維持しているため、気管が潰れることはありません。
何らかの原因で気管軟骨や気管の筋肉が弱まり、空気が通る際の圧力に負けて潰れることがあります。
これが気管虚脱です。
気管虚脱の原因については、遺伝によるもの、栄養など生活上のもの、炎症などが考えられていますが、今のところよくわかっていません。
犬では以下の犬種に多く見られますが、どの犬種でも起こる病気です。
- フレンチブルドック
- パグ
- ボストンテリア
- シーズー
- ヨークシャー・テリア
- トイ・プードル
- マルチーズ
- チワワ
気管が潰れると言っても初期の頃は少し歪む程度で、すぐに酸欠状態に陥ることはありません。
ただし、気管虚脱は進行性の病気なので、潰れる程度が少しずつ増していき、最終的には呼吸困難から亡くなってしまいます。
潰れやすくなった気管が元に戻ることはないため、外科手術以外での根治はできません。
進行速度には個体差がありますが、早い段階で見つけることができれば、適切な治療と生活面での配慮により、寿命と同じくらい生きることができた子もいます。
気管虚脱の末期症状
気管虚脱では、初期のころは喉の辺りを刺激すると咳をする、ガーガーとアヒルのような呼吸音がするなどの症状が見られます。
進行して気管の潰れ具合が増すと、呼吸が粗くなり、ハーハーと苦しそうに息をすることが増えるようになります。
症状は運動時や興奮時、睡眠時によく見られます。
末期になると、息を吸うときに気管が完全に潰れ、呼吸困難から酸欠状態に陥ります。
チアノーゼと呼ばれる、舌が青くなる酸欠状態が見られるのもこの頃です。



気管が完全に塞がると窒息し、突然亡くなってしまうこともあります。
気管虚脱の犬との生活で気を付けていただきたいこと
愛犬が気管虚脱と診断された場合は、生活の中で以下のことに注意しましょう。
太らせない
肥満は気管虚脱を悪化させる要因のひとつとされています。
すでに太っている場合は、食事管理などによるダイエットをしましょう。
太っていないとしても、太らないよう注意してください。
首輪ではなく胴輪を使う
首輪は引っ張ったときに気管が刺激され、咳が出やすくなったり、呼吸困難の原因になったりします。
サイズの合わない首輪が気管虚脱を誘発することもあるようです。
気管虚脱と診断された場合は、首輪は使わず、散歩は胴輪(ハーネス)を使いましょう。
激しい運動や興奮をさせない
激しい運動や興奮により激しく息をすることは、気管に負担をかけ、気管虚脱を悪化させます。
散歩では息が切れない速度にして、ボール投げなど激しい運動は避け、適度に休憩をとらせましょう。
吠え続けることも気管に負担をかけますので、自宅での居場所は落ち着いて過ごせるような静かな環境にしてあげてください。
散歩中に特定の家や、他の犬に吠えてしまうのであれば、コースを見直しましょう。
部屋の温度と湿度に気を付ける
温度が高すぎると熱中症のリスクが上がり、また、体温を下げるために口を開けて粗い呼吸をするため(パンティング)、呼吸困難に陥りやすくなります。
逆に寒すぎると咳が出やすくなるため、暑くも寒くもない、適度な温度を維持してあげましょう。
空気が乾燥していると気管の表面が乾き、咳が出やすくなります。
加湿器などを使って、自宅の中の湿度を上げてあげましょう。
仰向けで抱かない
仰向けの体勢は気管に負担をかけますので、仰向けで抱っこをしないようにしましょう。
末期状態の気管虚脱への緩和ケア
末期状態の気管虚脱に対する緩和ケアでは、少しでも楽に過ごせるように、酸素療法や、咳や炎症などを抑えるための投薬、ネブライザーによる薬剤の吸入や加湿などを行います。



訪問診療を利用すれば、移動の負担をかけずに治療を行えるでしょう。
酸素療法
潰れた気管では通常よりも肺に吸い込める空気の量が少ないため、効率的に酸素を取り込むために、高濃度の酸素を吸わせる酸素療法を行います。
人間の場合はチューブやマスクで吸入しますが、犬でそれは難しいため、空間全体の酸素濃度を上げる酸素室を使用します。
さまざまなメーカーからさまざまなサイズの在宅酸素室が出ており、レンタルも可能です。
在宅酸素室については、以前の記事でも紹介していますので、ご参考ください。


投薬
咳を抑える薬や、気管支を広げる薬、抗炎症薬などで、症状を緩和します。
内服が難しい場合は注射や、ネブライザーによる吸入療法も行います。
ネブライザー(吸入療法)
ネブライザーは液体の薬を霧状にして、気管や肺に直接届けるものです。
気管支を潤わせる効果もあるため、気管虚脱や気管支炎、肺炎などの治療でも使われます。
末期の気管虚脱などで酸素吸入が必要な場合は、ネブライザー付き酸素吸入器を使用します。
まとめ
今回は気管虚脱について、病気の概要と自宅で気をつけていただきたいこと、末期状態の気管虚脱への緩和ケアをお話ししました。
気管虚脱は進行性の病気で、はじめは症状は軽いものの、末期状態になると呼吸困難を起こし、突然亡くなってしまうこともあります。
末期状態では呼吸もかなり苦しくなりますが、酸素療法をはじめ、適切な緩和ケアを行えば、自宅で安心して過ごすことができるでしょう。当院は在宅緩和ケアの専門病院として、苦痛を減らし、穏やかに生活ができるお手伝いをしております。
訪問診療やオンライン/電話相談のほか、酸素室でも通院も行っております。
末期状態の気管虚脱の緩和ケア、訪問診療などについて、質問やご相談があれば、お気軽にご連絡ください。