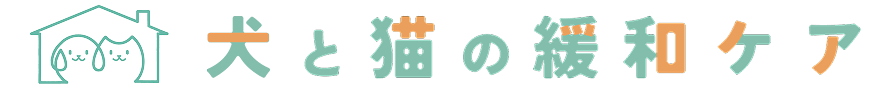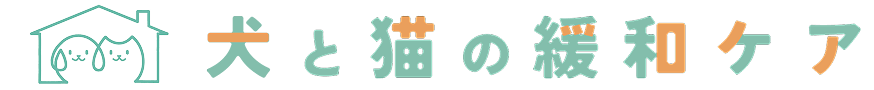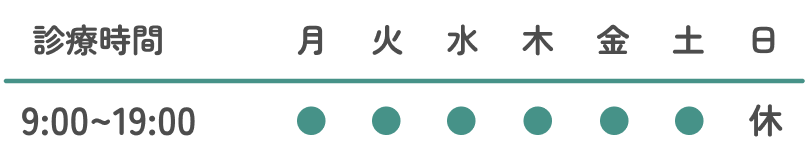犬の慢性腎臓病は初期症状がわかりにくく、診断されたときにはすでに進行しているケースが少なくありません。
慢性腎臓病は治る病気ではないため、病気とどう向き合っていくべきか不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
今回は犬の慢性腎臓病について
「この先どういう症状がみられるのか」
「どのような治療をするのか」
「家ではどうサポートしたらいいのか」
といった疑問を解決していきます。

ぜひ最後までお読みいただき、慢性腎臓病の愛犬のサポートに役立ててください。
犬の慢性腎臓病とは
腎不全とは、腎臓が十分に機能しなくなり、さまざまな症状がみられる状態のことです。
腎不全が長期間続く状態を慢性腎臓病といいます。
腎臓は尿をつくり、老廃物や余分な水分を排泄する臓器です。
腎臓がダメージを受けると老廃物や毒性物質が体内に蓄積するため、食欲不振や嘔吐などが起こります。
腎臓はダメージを受けても再生できないため、腎臓の機能が回復することはありません。
慢性腎臓病の末期症状
慢性腎臓病の初期は体調の変化に乏しく、病気に気づかないことも多くあります。
症状があったとしても飲水量や尿量が少し増えたり、食欲が少し減ったりする程度です。
進行していくと、水をよく飲み尿をよく出す多飲多尿という症状や嘔吐、食欲不振などが認められます。
末期になると、尿毒症による症状がみられます。
尿毒症とは腎機能の低下により尿毒素が体内に溜まり、全身にあらゆる障害を起こすことです。
尿毒症では
- 食欲不振
- 元気消失
- 嘔吐
- 下痢
- 口や体からのアンモニア臭
- けいれん
といったさまざまな症状がみられます。
また、腎臓は血液をつくるホルモンを出しているため、尿毒症では貧血も認められます。
犬の慢性腎臓病の治療


慢性腎臓病は治る病気ではないため、治療の目的は症状の緩和と腎臓病の進行の抑制です。
腎臓病を悪化させないため、また愛犬の苦痛を軽減するためにも、各症状に対処する必要があります。
慢性腎臓病で行われる治療は、体内に老廃物や尿毒素を溜めこまないようにする治療です。
具体的には
- 点滴
- 投薬
- 食事療法
といった治療です。
皮下点滴
慢性腎臓病では尿を濃縮する機能が低下するため、薄い尿がたくさん排泄されます。
水分を適切に摂取していても脱水しやすい状態です。
点滴により水分を補い脱水を改善することで、腎臓への負担を軽減できます。
皮下点滴は、血管ではなく皮膚の下に点滴する方法で、自宅でも実施できる治療です。
ただし、皮下点滴は心臓の負担になることもあるため、定期的に病院を受診し、点滴の量や頻度を調整しましょう。
いざ愛犬に皮下点滴をするとなると、疑問や不安があると思います。



皮下点滴を自宅で行っていただく際は当院がサポートいたしますので、ご安心ください。
投薬
慢性腎臓病では
- 蛋白尿の薬
- 毒素を吸着する薬
- リンを吸着する薬
- 高血圧の薬
- 貧血の薬
などが犬の状態に合わせて投与されます。
これらは症状を緩和するための薬です。
慢性腎臓病では腎機能の低下により、尿毒素やリンを体外に排泄しにくい状況です。
尿毒素やリンはさまざまな症状を引き起こしたり、腎臓病を悪化させたりします。
吸着剤を投与し、尿毒素やリンの排泄を促してあげます。
療法食
慢性腎臓病の食事は腎臓への負荷を軽減するために
- たんぱく質
- ナトリウム
- リン
を抑えた療法食が推奨されます。
しかし、慢性腎臓病では食欲が低下しているため、療法食を食べないケースも多くあります。
現在は色々なタイプの療法食が販売されていますので、食いつきが悪い場合は当院にご相談ください。
療法食を食べない場合は無理をせず、食べられるものを与えて構いません。
ただし、腎臓への負担が大きい食べ物もあるため、獣医師に相談しながら与えるようにしましょう。
自宅でできる緩和ケア
愛犬が慢性腎臓病と診断された場合、自宅ではどのようなケアを行えばよいのでしょうか。
ここでは、愛犬の症状を緩和するために自宅でできるケアについてご紹介します。
水分補給
慢性腎臓病は脱水しやすい状態であるため、水分補給が重要です。
水飲み場を犬が行きやすいところに設置するなど、水を飲みやすい環境をつくってあげることが大切です。
自力で飲むことが難しい場合は、スポイトなどで口から与えてあげましょう。
一気に入れると誤嚥してしまうので、少しずつ与えるのが望ましいです。
ドライフードでなくウェットフードを与えるのも、水分摂取を増やす方法のひとつです。
食事の介助
末期の慢性腎臓病では、吐き気や胃のむかつきなどから食欲が下がりがちです。
食べない状態が続くと衰弱していくだけでなく、腎臓にも負荷がかかります。
こういった状態が続くと腎臓病が悪化していくだけでなく、愛犬も飼い主様もつらいですよね。
衰弱や脱水を防ぐためには、少しでも食べることが重要です。
何も食べない場合は、流動食をスポイトなどで与えてみることをおすすめします。



流動食を受け入れてくれない場合や、与えるのが難しい場合は、いつでも当院にご相談ください。
温度管理
慢性腎臓病では代謝の低下などにより、体温が低下しやすい状態にあります。
体温が低下すると血行が悪くなったり、免疫や胃腸の働きが弱まったりします。
室温に気をつけるとともに、洋服や保温マット、犬用の湯たんぽなどを活用し、体温が低下しないよう注意しましょう。
なお、湯たんぽなどが犬に直接触れると低温やけどを起こす可能性があります。
タオルを巻くなどして低温やけどにならないよう気をつけましょう。
まとめ
慢性腎臓病は治る病気ではありませんが、適切なケアにより愛犬の苦痛を減らすことができます。
治療は長期的になる場合が多く
- どの治療をするのか
- どのくらいの頻度で通院するのか
- どこまで治療を行うのか
など悩むことが多いかと思います。
当院では愛犬が穏やかに過ごせるようサポートいたします。
些細なことでもお気軽にご相談ください。