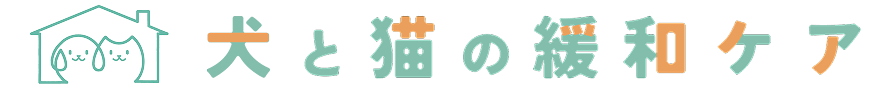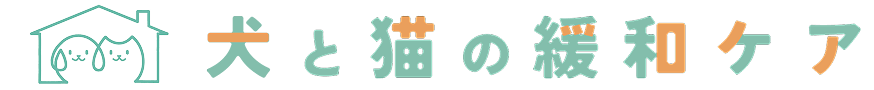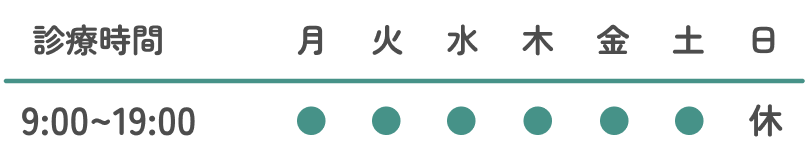犬のぶどう膜炎|悪化すると失明するぶどう膜炎について獣医師が解説
ぶどう膜炎という病気をご存知でしょうか?
ぶどう膜炎とは、眼の一部であるぶどう膜という組織で炎症が起きる病気です。
犬では様々な原因でぶどう膜炎になってしまうことがあります。
ぶどう膜炎が悪化すると、眼の痛みや視力の低下がみられ、犬も飼い主様もつらい思いをされてしまうかもしれません。
今回は、犬のぶどう膜炎の原因や治療、治療が上手くいかないときにできることについてお伝えします。
犬のぶどう膜炎とは
眼球には、虹彩・毛様体・脈絡膜という組織があり、これらを合わせて「ぶどう膜」と呼びます。
ぶどう膜は血管が豊富で、目の中に栄養や酸素を届ける大切な役割を担っています。
このぶどう膜で炎症が起きている状態が「ぶどう膜炎」です。
ぶどう膜炎では、次のように様々な眼の症状がみられます。
- 白目が充血している
- 黒目が白く濁って見える
- 黒目が小さい
- 涙が多い
- 目が開きづらそう、痛そうにしている
- 目が見えづらそうな様子(物にぶつかる、動きが減るなど)がある
初期には、ただの充血にみえることもあり、見逃されてしまうケースも少なくありません。
ぶどう膜炎が進行すると、白内障や緑内障など、他の眼の病気を合併してしまうことがあります。
最終的には失明してしまう可能性もあるため、早めに気付いて治療してあげられると良いですね。
ぶどう膜炎には他の病気が隠れていることが多い
ぶどう膜炎は、何か他の病気に合併して起きることが多いのが特徴です。
原因として多いのは、次のような眼の病気ですね。
- 外傷(角膜潰瘍・角膜穿孔)
- 白内障
- 眼の腫瘍
眼だけの問題ではなく、全身の病気が原因でぶどう膜炎になってしまうこともあります。
代表的な原因疾患をみていきましょう。
- 糖尿病
- 感染症(子宮蓄膿症など)
- 免疫介在性疾患
- 高脂血症
- 高血圧
中には、原因疾患が見つけられない場合もあり、特発性ぶどう膜炎(原因不明)と診断されます。
ぶどう膜炎自体は命に関わるものではないですが、ぶどう膜炎の原因によっては早急な治療が必要であることもあります。
ぶどう膜炎の治療
ぶどう膜炎が進行して、白内障や緑内障などの病気を合併してしまうと、治療がより難しくなってしまいます。
そのような状態にならないためにも、早めに診断・治療してあげられると良いですね。
ぶどう膜炎の治療は、「ぶどう膜炎の症状を抑える治療」と「原因疾患の治療」を同時に行っていきます。
ぶどう膜炎の症状を抑える治療
症状を抑える治療でメインとなるのは、抗炎症薬(ステロイド剤、非ステロイド性抗炎症薬)の投与です。
点眼薬を使うことが多いですが、状態に応じて内服薬も使います。
散瞳剤(瞳孔を開く薬)の投与も、ぶどう膜炎の症状を抑える効果があります。
原因疾患の治療
原因疾患が明らかなぶどう膜炎の場合、原因疾患をしっかりと治療することが重要です。
いくら炎症をおさえる治療を頑張っても、原因疾患が治療できていないとぶどう膜炎の再発を繰り返すことになってしまいます。
治療内容は原因疾患により様々です。
難治性の場合にできること
ぶどう膜炎の中には、残念ながら治療が上手くいかず、難治性となってしまうケースもあります。
難治性の場合には、緩和療法(症状や合併症をできるだけ抑えて、犬の苦痛を取り除く治療)を行います。
難治性のぶどう膜炎では犬が失明してしまうことも少なくありません。
失明してしまった犬とともに生活するうえでできることについてもみていきましょう。
緩和療法
緩和治療においても、治療の主体は抗炎症薬(ステロイド剤、非ステロイド性抗炎症薬)です。
薬の副作用が出ないように、なるべく少ない用量で投薬を続けていきます。
眼の状態に応じて、症状や合併症を抑える他の薬もあわせて投与します。
このような投薬を続けても、残念ながら症状が抑えられないこともあります。
眼の痛みのせいで元気や食欲が落ちてしまうと、犬も飼い主様もつらいですよね。
すでに視力が失われてしまい、症状の管理も難しいときには、眼球摘出手術もひとつの選択肢です。
可愛いお顔の見た目が変わってしまうので、つらい選択にはなってしまいますが、苦痛を取り除く方法のひとつとして考えておきましょう。
ぶどう膜炎の炎症が落ち着いているときには、義眼を入れて見た目を保つこともできるかもしれません。
失明してしまった犬との生活でできること
犬が失明してしまうと、これまで通りの生活ができるのか不安になりますよね。
飼い主様が生活の工夫をしてあげることで、失明してしまっても慣れや他の感覚を頼りに日常生活を送ることができます。
失明した犬となるべく快適に暮らすために、飼い主様にできることをみていきましょう。
眼が見えないと、物にぶつかって怪我をしてしまう危険があります。
慣れている部屋にいてもらうようにして、ごはんやトイレなど物の配置を変えないようにしましょう。
エリザベスカラーの装着やクッションの設置も、怪我を防ぐために良い方法ですね。
散歩にも行くことができますが、コースはいつも同じにして、段差や溝のある道は避けることをおすすめします。
視覚を失った犬は、聴覚や嗅覚など他の感覚を頼りに生活します。
突然触られたり、リードを引っ張られたりすると驚いてしまうので、先に声をかけてあげてください。
ごはんは匂いでわかるように、鼻の近くまでもっていってあげましょう。
まとめ
ぶどう膜炎は、原因をつきとめて治療できれば、改善が期待できる病気です。
一方で、残念ながら難治性となってしまう場合もあります。
そのような場合でも犬と飼い主様がなるべくつらい思いをしないように、できることがないか一緒に考えていきましょう。
治りにくいぶどう膜炎でお困りの方は、お気軽にご相談ください。