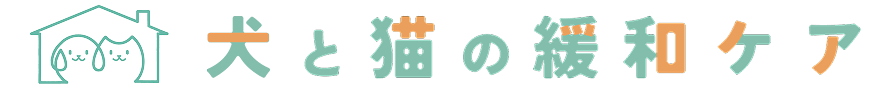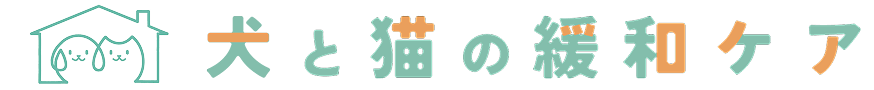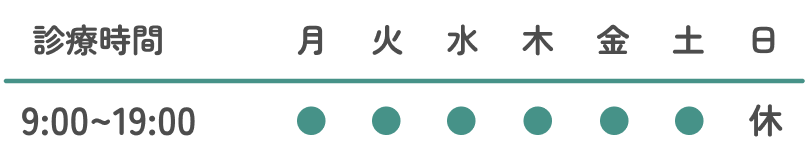犬は視力が落ちても、普段の様子にあまり変化が見られないことも多く、気づいたときにはすでに失明していたというケースも珍しくありません。
ある日突然、愛犬の目が見えていなかったことを知り、戸惑いや不安を感じる飼い主さんも多いのではないでしょうか。
「これまで通りの生活はできるの?」
「何に気をつけて暮らせばいいの?」
「愛犬が落ち込んでしまうのでは?」
と悩むこともあるかもしれません。
しかし、犬は聴覚や嗅覚が優れているため、視力を失ってもその他の感覚で十分に補うことができます。
適切なサポートをしてあげれば、今までと変わらない暮らしをすることも可能です。
今回は犬の失明について解説したうえで、失明後のケアや生活の工夫についてご紹介します。

ぜひ最後まで読んでいただき、失明した愛犬をサポートするためのヒントを見つけてください。
犬の失明の原因
犬が失明する原因は多岐にわたり、目の病気だけではありません。
視覚は水晶体、網膜、視神経、大脳という順に情報が伝わっていきます。
この経路のどこかに異常が生じると、失明が起こるのです。
眼球そのものに原因がある場合だけでなく、
- 脳腫瘍
- 脳炎
- 高血圧
- 薬物中毒
などによっても失明することがあります。



ここでは、失明を起こす代表的な病気について器官別に分けて解説します。
水晶体の病気
犬でよく見られる水晶体の病気として白内障があります。
白内障とは水晶体が白く濁ってしまう病気です。
水晶体はレンズの部分であり、本来は透明で光を通すところです。
白内障の初期では水晶体の濁りが少ないため、視覚はまだ保たれています。
しかし、進行するにつれて視力は徐々に低下し、最終的には失明に至ります。
白内障の原因は
- 加齢
- 遺伝的要因
- 糖尿病による合併症
- 目の外傷や炎症
などさまざまです。
白内障は早期に発見し、適切に治療をしてあげれば治すことができる病気です。
「最近目が白っぽくなってきた」と感じたら、早めに動物病院を受診しましょう。
網膜の病気
目の奥にある網膜は、視覚を感じとるうえで重要な役割を担っています。
網膜が徐々に薄くなり、最終的に失明に至る病気が進行性網膜萎縮(PRA)です。
PRAは遺伝性の疾患であり、特にミニチュア・ダックスフンドやトイ・プードルなどの犬種に多い病気です。
残念ながら、現在のところ有効な治療法はなく、予防も難しいとされています。
早期に発見された場合には、進行を緩やかにすることを目的としてサプリメントを使用することがあります。
この病気を広げないためにも、PRAの遺伝子を持つ犬を繁殖に使わないことが重要です。
このほかに網膜の病気で失明を引き起こすものとしては、突発性後天性網膜変性症(SARD)や網膜剥離などが挙げられます。
視神経の病気
代表的な視神経の病気として緑内障があります。
目の中には眼房水と呼ばれる液体が循環していて、角膜や水晶体に栄養を届けています。
眼房水がうまく排出されず、眼球内に過剰にたまってしまう病気が緑内障です。
緑内障になると眼房水がたまり、眼圧が上昇するため、強い痛みを伴うことがあります。
眼圧の上昇によって視神経がダメージを受けると、視覚に障害が起き、治療が遅れると失明に至る可能性もあります。
緑内障は早期発見と早期治療が非常に重要です。
進行が早いケースもあるため、
- 目が大きくなっている
- 白目が充血している
- 目が大きいように見える
- 瞳孔が明るい場所でも開いている
といった症状が見られたら、できるだけ早く動物病院で診てもらいましょう。
目が見えないときの症状
犬は視覚がかなり低下するまで、行動に大きな変化は見られません。
特に片目だけ失明している場合は、失明に気づかないことも多くあります。
しかし、視覚の低下に伴って徐々に行動に変化が見られるため、早めに異変に気づいてあげることが大切です。
具体的には以下のような様子が見られます。
- 物にぶつかる
- 段差につまづく
- ボールなどのおもちゃへの反応が鈍くなる
- あまり動かなくなる
- 目が合わない
- 散歩に行きたがらない
このような変化に気づいたら、早めに動物病院を受診しましょう。
失明している犬へのケア
犬は視覚以外の嗅覚や聴覚が非常に優れているため、目が見えなくなっても意外と普段どおりに生活することができます。
とはいっても、サポートをしてあげないと生活の質(QOL)が低下したり、思わぬケガや事故につながったりする場合もあります。



では、具体的にどのようなケアをしてあげればよいのでしょうか。
生活環境を変えない
失明した犬が安心して過ごすためには、生活環境を変えないことが重要です。
慣れている場所で安心して暮らせるように、以下の点に注意してあげましょう。
- 家具の配置を固定する
- 犬の通り道に物を置かないようにする
- 角や尖った部分にはクッション材をつける
- 階段や段差にはゲートを設置して立ち入りを防ぐ
- 食器や水飲み場の位置を変えない
慣れている環境を変えないことが大切です。
積極的に声をかける
目が見えない犬は、突然触られると驚いてしまいます。
ストレスを与えないためにも、犬に近づくときや触れるときは、優しく声をかけてあげましょう。
また、犬が移動する際にも名前を呼んだり声をかけたりすることで、安心して動くことができ、進む方向もわかりやすくなります。
日常の活動を続ける
視力が低下すると、犬はあまり動きたがりません。
しかし、散歩や遊びなど犬が楽しめる活動を続けることは、心のケアとしても大切です。
散歩はいつも同じルートにしてあげると、安心して散歩に行くことができます。
散歩を嫌がるようであれば短いコースにしたり、抱っこで外の空気を感じさせたりするだけでも十分です。
遊びでは音の出るおもちゃなど、視覚に頼らない遊び道具を使ってあげるとよいでしょう。
無理のない範囲で体を動かしてあげることは、肥満や筋力低下の防止にもつながります。
まとめ
犬の失明は、QOLが大きく低下することも少なくありません。
目が見えなくなっても、愛犬にはできるだけ普段と変わらない生活を送らせてあげたいですよね。
お家での対策やケアをしっかり行うことで、愛犬が快適に過ごせる環境を整えることができます。
また、定期的に目の状態をチェックしてあげることも重要です。



どうしたらいいのかわからない、目のことで不安がある場合は、お気軽に当院までご相談ください。