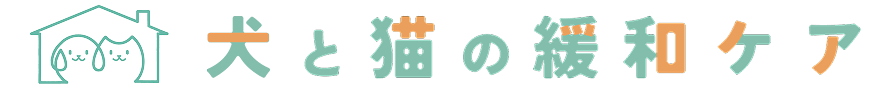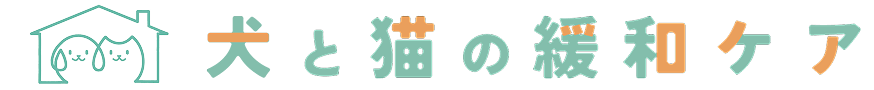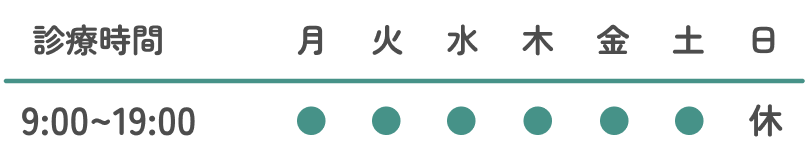「乳腺にしこりがある気がする」
「もしかして乳がん?」
飼い主様が愛犬の体をなでているとき、ふとしたきっかけで気づくことが多いのが乳腺腫瘍です。
こうした何気ない触れ合いが、命を救う第一歩になることもあります。犬の乳腺腫瘍は、雌犬で最も多く見られる腫瘍です。
良性・悪性を問わず、乳腺の周囲にしこりができるのが特徴で、多くの場合は手術による治療が選択されます。
しこりの大きさや性質には個体差があり、早期発見・早期対応が大切です。
今回は乳腺腫瘍について詳しく解説していきます。

ぜひ最後までお読みいただき、乳腺腫瘍の早期発見に役立ててください。
犬の乳腺腫瘍の原因は?
乳腺腫瘍は、性ホルモンの影響を強く受ける病気と考えられています。
とくに避妊手術をしていない高齢の雌犬では、発情を繰り返すことでホルモンの刺激を受け続け、発症リスクが高まる傾向があります。
また、発症の平均年齢は10〜11歳とされており、年齢とともにリスクは上昇する腫瘍です。



とはいえ、はっきりと原因は分かっていないことも多いです。
犬の乳腺腫瘍の発症は?
犬の乳腺腫瘍は、約半分が良性、残り半分が悪性といわれています。
さらに悪性のうち、約50%は転移を起こしやすく進行も早いため注意が必要です。とくに未避妊の雌犬で中〜高齢になると、乳腺にしこりが見つかる機会が増えてきます。
なかには肺やリンパ節に転移しているケースもあるため、小さなしこりでも放置せずに早めの検査が大切です。
犬の乳腺腫瘍の症状は?
犬の乳腺腫瘍の症状としてもっともよく見られるのは、乳腺周囲に触れるしこりです。
しこりは柔らかいものもあれば、硬くゴツゴツとした感触のものもあります。
見た目や触り心地だけでは良性か悪性かを判断するのは難しいでしょう。悪性の場合、しこりが急に大きくなったり、周囲に炎症が広がったりすることがあります。
とくに「炎症性乳がん」と呼ばれるタイプでは、以下のような症状が現れやすくなります。
- 強い炎症と赤み
- 痛み
- 腫瘍部分の皮膚のただれ
このタイプは進行が早いため、できるだけ早く治療を開始する必要があります。
しこりを見つけた場合はなるべく早めに動物病院へ相談しましょう。
犬の乳腺腫瘍の診断は?



犬の乳腺腫瘍はどのように診断するのでしょうか?
まずは触診でしこりの大きさや硬さ、場所を確認します。
続いて、いくつかの検査を組み合わせて、腫瘍の性質や広がりを調べます。
- 細胞診:針で細胞を採取して顕微鏡で観察。ただし良悪性の判断は難しいことも。
- レントゲン・エコー検査:肺やお腹への転移がないかを確認。
- 病理検査:手術で取り除いた腫瘍を詳しく調べ、最終的な診断をつける。
とくに病理検査は腫瘍が悪性か良性かを判断する大切な検査です。
たとえば「乳腺癌」や「良性乳腺混合腫瘍」といった診断名がつきます。
また、腫瘍がきちんと取り切れているかの確認も、病理検査で行われます。
乳腺癌


良性乳腺混合腫瘍


犬の乳腺腫瘍の治療は?
乳腺腫瘍の治療の中心となるのは外科手術です。
腫瘍の数や広がりによって、切除の範囲が変わってきます。
- 腫瘤だけを取る「腫瘤切除」
- 一つの乳腺を取る「単一乳腺切除」
- いくつかまとめて取る「領域乳腺切除」
- 片側または両側を一括して取る「片側乳腺切除」「両側乳腺切除」
また、乳腺腫瘍の手術を実施した際は卵巣(子宮)の摘出手術を同時に行うことがおすすめです。
これはホルモンの影響を断ち、再発リスクを下げるための処置です。
犬の乳腺腫瘍の治療のみとおしは?
乳腺腫瘍は良性腫瘍の場合や、転移・浸潤のない悪性腫瘍であれば手術後の経過は良好です。
ただし、転移が見られる場合や炎症性乳がんの場合は、どうしても予後が厳しくなります。
治療後も定期的に検診を受け、肺やリンパ節などに変化がないか確認していくことが大切です。
「取ったから終わり」ではなく、「取ったあとをどう見守るか」が、愛犬の命を守る鍵になります。
乳腺腫瘍を手術で摘出した後もきちんと病院で経過観察を行っていくようにしましょう。
- 病理検査にて、良性腫瘍と浸潤のない悪性腫瘍は予後良好
- 病理検査にて、浸潤・転移のある腫瘍は転移部の大きさの変化などに注意
- 炎症性乳がんは予後が悪い
まとめ
犬の乳腺腫瘍は、しこりが見つかった時点でできるだけ早く検査・治療に進むことが重要です。
良性でも悪性でも、早期に対応できれば予後が良くなる可能性が高まります。
愛犬の体をなでるとき、ふとした触診が早期発見のきっかけになるかもしれません。



「あれ?」と思う変化があったら、どうか早めにご相談ください。